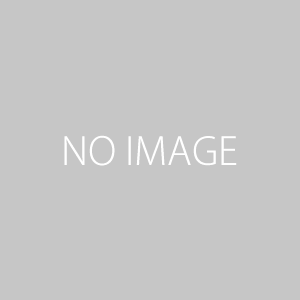河合塾講師が語る!2025年度新課程入試 ―地理編―[後編]
■ コラム②:本に描かれた風景を探して世界を旅する
――地理関連に限らず、先生がおすすめしたい本やよく読んでいた本をご紹介ください。
マルグリット・ユルスナール(フランスの作家、1903 – 1987)の『ハドリアヌス帝の回想』は、地理と歴史の両者がうまく絡み合ったとても面白い作品です。私は須賀敦子の『ユルスナールの靴』というエッセイで知りましたが、彼女の訳文は非常に優れています。須賀敦子自身の著作も、どれもたいへん素晴らしいです。
――先生は、文学作品もお好きだったのですね。
いろいろな本を読むようになったのは、現在の仕事に就いてからです。予備校講師になりたての頃は授業も少なく、時間的にかなり余裕があったため、空いた時間で本をたくさん読んでいました。河合塾の先生同士が本をおすすめし合っているのを横から聞いていて、「じゃあ読んでみるか」と思ったのがきっかけです。あの時間がなかったら手に取ることすらなかった本もたくさんあったと思うので、多くの良き出会いに恵まれた「有意義な空き時間」だったと思います。
けれども、今は文学作品を読むこともほとんどなくなってしまいました。「読んでいていいのか?仕事に関する本で、他に読むべきものがあるんじゃないのか?」と思ってしまって…。
――社会人によく聞かれる話ですね。
そうですよね。そのため、最近は文学作品を読まなくなっていますが、高校、大学、それから予備校講師になってすぐの頃は、本当にたくさんの本を読みました。
――各作家のどのような点がお好きなのでしょうか。
須賀敦子の作品は、エッセイも含め、ほぼ全て読んでいるのですが、彼女の風景描写にはいつも感動します。それは、単にミラノの街角の風景を説明している文であるはずなのに、読んだ瞬間、「これは見に行かねば!」という気持ちが湧き起こるほどです。その豊かな表現に魅了され、本に描かれた景色をこの目で見ようと、期待に胸を弾ませ現地を訪れたことは数知れず。けれどもそのたび、本物のあっけなさに肩を落としてきました。それほどまでに、彼女の描き出す風景は魅力的なのです。
高校から大学にかけては、三浦綾子を愛読していました。彼女の作品における「原罪」についての記述には、かなり影響を受けています。
ほかにも、ロシア語通訳者である米原万里のエッセイ、『嘘つきアーニャの真っ赤な真実』もおすすめです。彼女の文章に感銘を受け、ベオグラードに6度赴き、「この文章に描かれた景色はいったいどこから見られるのだろう」と、あちこち探し回りましたが、結局見つけられませんでした。彼女の景観表現も、須賀敦子同様、たいへん素晴らしいと思います。
米原万里は、一冊だけ小説も執筆しています。『オリガ・モリソヴナの反語法』という、第二次世界大戦後の社会主義国について扱った作品です。チェコを中心とする景観の分析も見事で、例に漏れず、本を持参して現地へ行き、描かれた風景を探しては、「無いじゃん、これ!」といったことを繰り返しています。
▶2025年度共通テスト結果分析、地理の重要テーマと作問上のジレンマ、出題者と受験生それぞれの視座に立った「共通テスト地理」論が展開される[前編]はこちら
松本 聡(まつもと・さとる)先生

プロフィール:
河合塾地理科講師。中部地区所属。授業は、講義・演習・ゼミなど幅広く担当。教材作成、入試分析等にも携わる。
愛知大学文学部史学科地理学専修コース卒業。
著書:
・『大学受験 ココが出る!! 地理ノート 地理総合,地理探究 改訂版』(旺文社,2023年)
・『一問一答 地理 ターゲット 2500 改訂版』(旺文社,2021年)
・(共著)『地理用語完全解説G』 著者:伊藤 彰芳/松本 聡/瀬川 聡(河合出版,2019年)
・教室シリーズ『松本聡の地理教室』(旺文社,2018年)
インタビュー・執筆・編集:山口夏奈(KEI大学経営総合研究所 研究員)
インタビューアシスタント:原田広幸(KEI大学経営総合研究所 主任研究員)