
河合塾講師が語る!2025年度新課程入試 ―世界史編―[後編]
■ コラム③:新科目における歴史的事象の関連性への気づきの獲得と、批判的精神養成への懐疑
――グローバルヒストリーが近年隆盛を極めていますが、ジャレド・ダイアモンド氏やユヴァル・ノア・ハラリ氏の著書などは、高校の世界史学習との関連はあるのでしょうか。
少しずれてはいますが、興味のある人は読むと面白いと思います。教科書とはまた違った歴史の捉え方があると知ること、「こういう考え方もできるのか」という発見は、歴史学習において非常に重要ですから。
――先生が学生時代にお読みになった本で、「この歴史学の本に大きな影響を受けた」とか「非常に勉強になった」というものをぜひご紹介ください。
完全に時代が出てしまうのですが、網野善彦先生の本はよく読んでいました。今となっては古典ですけどね。同時代で言うと、私の研究指導をしてくださった谷川道雄先生の本も読んでいましたし、私の専攻は中国史でしたから、宮崎市定先生の本もたくさん読みました。特に宮崎先生の文章は非常に軽快で、私は読みやすかったです。今や古典の古典の、さらに古典くらいの方ですけどね(笑)。
――宮崎市定先生の書きぶりは軽快なのですか!それなら初心者でも読めそうですね。
私にとっては軽快でしたね。初心者でも読めると思います。
――昔は歴史科目といえば、「暗記科目」「一問一答」というイメージでしたが、今回の改訂で『歴史総合』『日本史探究』『世界史探究』になったことにより、高校の段階から、自ら思考し、多角的に考察するという、いわゆる大学での勉強に近づいたような印象を受けています。その点において、知識や教養を身につけるだけでなく、文化的・学術的な刺激を得たり、いわゆる高大接続的な学びを実践したりするという意味でも、高校における歴史科目の重要性が増しているように思いました。
そう言われると、私の仕事の存在意義がとてもある気がします(笑)。
例えば、昨年の大学受験科生は、2025年度共通テストを旧課程科目で受験する生徒たちでしたが、二次試験の出題も考慮して、適宜『歴史総合』『世界史探究』的な要素も含んだ授業を行っていました。そうすると、地域横断的な話をしたときに、非常に良い反応が返ってきます。「今まで年号で覚えていました」「用語だけ覚えていました」「国の名前は知っていました」。そうした個々の知識でしかなかったものが、「このような関連性で並んでいて、こうつながっているのか」と開けて見えた時に、生徒たちは感動するようです。
歴史的事象の関連性に気がつくきっかけとして『歴史総合』『世界史探究』が機能しているのであれば、それは良いことだと思いますし、進路として歴史学を選ばないとしても、次のステップへ進むときの基礎的な素養・態度として、そうした歴史、あるいは物事の見方が身についていることはとても大切だと思います。
――いわゆる「比較○○学」の初歩のような勉強を高校生のうちに経験できるようになったということですね。
しかしながら、『歴史総合』『世界史探究』を通して批判的な精神が正しく養成され得るのかについて、現時点では個人的に「ペンディング」です。学習指導要領解説に、資料を批判的に読み取る力を身につけさせることが重要である旨の記述が見られますが、実際の入試問題などを見ると、示されている資料はすべて正しいという前提のもと扱われています。
主体的な学びの重要性が説かれる一方で、資料はすべて正しいものとして扱われていたり、自身の発言がすべて容認されたりする状況の中で、批判的なものの見方が果たしてどれほど育つのでしょう。牙を抜かれたような人が量産されるだけではないのか。そういった懸念を、私は少し抱いています。
とは言え、自ら考え、わかりやすく説明するといった学習を、今までそのような学びがほとんど行われてこなかった「歴史」という科目で実践すること自体は、生徒たちにとって刺激的に違いありません。『歴史総合』『世界史探究』になったことで、高校生のうちにそうした思考力・判断力・表現力が求められるような学びを経験できるようになったのは、面白いし意義があることだと思います。
――人文学の分野において、従来は方法論のようなものを学べる機会はそれほど多くなかったと思いますが、『歴史総合』『日本史探究』『世界史探究』での学びが、その良いきっかけになるのではないかと、先生のお話をうかがって期待が高まりました。
そうなっていくと良いですね。
◀共通テスト世界史科目のポイント、2025年度共通テスト結果分析、各大学個別試験における新課程への対応状況が語られる前編はこちら
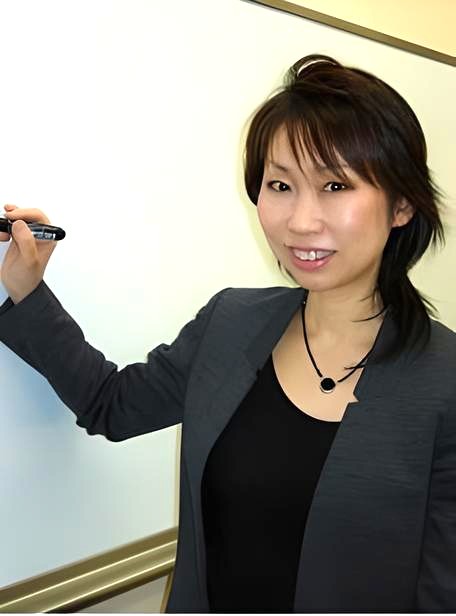
井上 徳子(いのうえ・のりこ)先生
プロフィール:
河合塾世界史科講師。近畿地区所属。授業は、講義・演習・ゼミなど幅広く担当。教材作成、入試分析等にも携わる。
京都大学文学部卒業。京都大学大学院文学研究科 博士後期課程 単位取得退学。学生時代の専攻は、五胡十六国時代史。
著書:
『判る! 解ける! 書ける! 世界史論述(三訂版)』河合出版(2025年)
『世界史最強の一問一答: 地図・論述・難関用語もこれ1冊で』河合出版(2019年)
インタビュー・執筆・編集:山口夏奈(KEI大学経営総合研究所 研究員)
インタビューアシスタント:満渕匡彦(KEI大学経営総合研究所 上席研究員)・原田広幸(KEI大学経営総合研究所 主任研究員)










