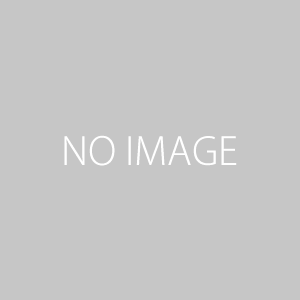河合塾講師が語る!2025年度新課程入試 ―世界史編―[後編]
河合塾 世界史科講師 井上徳子先生インタビュー【独自記事】
平成30年(2018年)に告示された新学習指導要領。その中でとりわけ大きな改訂がみられた科目の一つに『歴史』が挙げられる。従来の『日本史A』『日本史B』『世界史A』『世界史B』から『歴史総合』『日本史探究』『世界史探究』へと再編成がなされ、主体的で多角的な学びが強調されたほか、特に『歴史総合』においては、日本史と世界史の相互関連性がこれまで以上に重視されるようになった。
2025年度の大学入試は、新課程入試の初年度であると同時に、今回の課程変更の集大成とも言えるものである。そこで我々は、2025年度入試に関する河合塾講師へのインタビュー取材を実施した。
世界史編の後編では、河合塾世界史科講師:井上徳子先生に、課程変更に伴う生徒の視点や出願傾向の変化の有無のほか、大学教育に期待すること、井上先生が考える「世界史の力」と「人文学を学ぶ意義」について熱く語っていただいた。コラム「なぜ歴史は古い時代から順に学ぶのか」は、その意味を深く考えさせられる、非常に示唆に富む論である。
【目次】
■ 高校現場と入試の間にある『歴史総合』の温度差(課程変更に伴う生徒の変化の有無①)
■ 受験時の科目選択、志望動向への影響(課程変更に伴う生徒の変化の有無②)
■ コラム②:なぜ歴史は古い時代から順に学ぶのか
■ 大学には多様な学びを提供できる場所であり続けてほしい
■ 歴史とは、先人が命をかけて壮大な実験をしてくれた場の集積である
■ 人文学系の学問は「船の錨」
■ コラム③:新科目における歴史的事象の関連性への気づきの獲得と、批判的精神養成への懐疑
◀共通テスト世界史科目のポイント、2025年度共通テスト結果分析、各大学個別試験における新課程への対応状況が語られる前編はこちら
■ 高校現場と入試の間にある『歴史総合』の温度差(課程変更に伴う生徒の変化の有無①)
――ここからは、課程変更に伴う生徒の変化をテーマにお話をうかがいたく存じます。
私がメインで教えているのは大学受験科生(いわゆる既卒生)です。高校3年生の授業も一部担当していますが、近畿圏の私立大学を第一志望とする生徒が多いため、本年度、彼らの受験に『歴史総合』はほとんど関係しませんでした。それゆえ、「課程変更に伴う生徒の変化」として、今回どれだけリアルな反応をお伝えできるかは正直分かりません。けれども、私を含めて皆が共通して思っているのは、『歴史総合,世界史探究』で受験をする場合に、日本史の内容をどこまで深く追究しておくべきか、その匙加減が悩みどころだということです。
――それは「教える側として」ですか。
教える側もですし、受け止める側、つまり生徒的にもそうですね。そして、おそらくその悩みは、日本史メインで受験する生徒の方が大きいと思います。例えば、慶応義塾大学の日本史の問題を見ると、『歴史総合』の範囲でかなり世界史の内容が出題されていました。日本史での受験といえども、世界史の内容もしっかりと学んでおく必要がある点で、受験生にかかる負担はかなり大きいと思います。
――おっしゃるように、「どこまでの深さで教えるのか/学ぶのか」という悩みも当然あるかと存じますが、『歴史総合』が必履修になり、日本の歴史と世界の歴史を相互関連的に学ぶようになったことで、生徒の視点や考え方に変化が見られ始めたりはしているのでしょうか。
現時点では、これまでの生徒たちと何かドラスティックに違うという印象はありません。ただ一つ、今までにない反応だと思ったのは、高校3年生の『世界史探究』の授業で、古代から順に学んで近現代史に入ったときに、「知ってるところにたどり着いてほっとした」という声が結構聞かれたことです。例年、近現代史に入るのは10~11月頃で、受験直前ということもあり、いつも生徒たちから漂っていたのは「最後までやり切れるのだろうか」という不安感でした。だから、近現代史にたどり着いて、生徒たちから安堵の空気を感じたのは初めての経験でしたね。
また、生徒の視点や考え方の育成に最も関係するのは高校の授業です。高校の授業でどれだけ探究的な学習を実践できているかが、彼らの視点の変化に直結します。その意味で、教科書が「探究」になっても、授業がこれまでと変わっていない場合は、生徒の視点や考え方も、なかなか変わらないのではないでしょうか。
そうした中で、入試における探究的な問題の増加が、高校の授業が変わる一つのきっかけとなるかもしれません。入試の変化により、高校の先生方が探究学習の必要性を再認識し、授業が変わっていく。その授業の変化に伴って、生徒の視点や考え方も変化していく。この流れが生まれてくるのはこれからです。よって、今後徐々に生徒の視点に変化が見られてくる可能性はあると思います。
しかしながら、本来、高校の授業は入試のためにあるのではありません。高校の授業における真の目標は、『歴史総合』『世界史探究』の学びを通して、生徒に探究する力を身につけさせることです。そうして高校で探究する力を育んだ人たちが、その力を生かし、次のステップで活躍していってくれれば、それで良いのだと思います。だから本当は、高校の授業が入試に左右されるのは本末転倒なのです。
ただし、その入試に関しても、個別試験における出題科目の設定の仕方には思うところがあります。特に『歴史総合』の扱われ方はひどいものです。入学後の学びや学習指導要領を考慮した学問的な判断ではなく、募集への影響や他大学の判断に追随する形でのみ、『歴史総合』の出題有無を決定している大学も、残念ながら中にはあると感じています。学習指導要領に「『歴史総合』という土台あっての『日本史探究』『世界史探究』である」と明記されているにもかかわらず、です。
このように、高校現場に求められている『歴史総合』と、受験で扱われている『歴史総合』の間には明確な温度差があります。しかも、その扱われ方は大学によって大きく異なるため、振り回される受験生がかわいそうでなりません。生徒たちが『歴史総合』をただの負担に感じてしまうのも無理はないでしょう。
けれども、そうした温度差に関係なく、高校での学びを通して生徒自身が『歴史総合』を重要だと感じたのであれば、それは評価すべき判断だと私は思います。