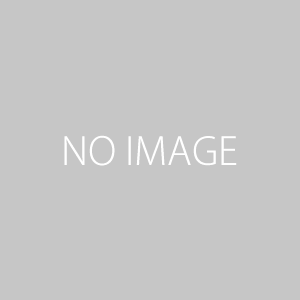河合塾講師が語る!2025年度新課程入試 ―地理編―[前編]
■ 『地理総合』で身につけた思考力を試すための出題形式とは -共通テスト『地理総合,地理探究』結果分析①-
――お話いただいた学習指導要領改訂のポイントも踏まえて、ここからは具体的に、2025年度入試のトピックスや、課程変更に伴う入試問題の変化についておうかがいします。まず共通テストについて、『地理総合』の範囲に対する先生の所感を教えてください。
2025年度共通テスト『地理総合,地理探究』において、『地理総合』からの出題であったのは、第1問と第2問です。テーマは「食料の生産や消費」と「地域調査」でした(出題科目『地理総合/歴史総合/公共』との共通問題)。共通問題となるテーマの方向性が、試作問題とはやや異なっていましたが、妥当な分野からの出題であったと思います。*
*試作問題における共通問題は、「難民問題」ならびに「自然環境と防災」をテーマとするものであった。
河合塾|2025年度 大学入学共通テスト速報
独立行政法人 大学入試センター|令和7年度 本試験の問題
*独立行政法人 大学入試センター|令和7年度試験の問題作成の方向性、試作問題等
出題形式としては、「一つの問題に一つの資料」という、いわゆる旧センター試験型の問題が多かった印象です。『地理総合,地理探究』の受験者にとっては、比較的解きやすい問題が並んでいたのではないでしょうか。中でも、第1問 問1の正答率はとても高く、89.6%に上りました(以下、正答率およびマーク率は、河合塾「共通テストリサーチ」における『地理総合,地理探究』受験者の結果に基づく)。
シンプルな出題形式が多かったため、思考力測定の点で懸念される方もいるかもしれませんが、『地理総合』の学習を通して身につけるべき思考力を試す分には、この形式で十分であったと私は思います。
『地理総合』で育成が求められている思考力は、『地理探究』で求められているものほど高次ではありません。けれども、それは地理学習の基礎をなす、非常に重要な資質・能力です。また、望ましい試験の在り方とは、学んだ内容や身につけた資質・能力が正しく測定できるものであるはずです。これらを踏まえると、『地理総合』の問題に、『地理探究』と同等の形式的な複雑さは不要なのかもしれないと思いました。普段、作問もする側の人間として、非常に考えさせられましたね。
共通テストになって以降、その出題形式は非常に複雑化しています。全ての問題で図や表などの資料が用いられ、複数の資料を組み合わせて考えるタイプの問いも増加しました。こうした問題で受験生の思考力を試そうとしていることは理解しますが、その複雑な出題形式は、地理での受験を考える生徒が最初に直面する大きな壁となっています。学習内容面ではなくテクニック面が、今や最大の関門となっているのです。
複雑な出題形式をクリアできない受験生を、共通テストは土俵に上げてはくれません。どんなに一生懸命地理の勉強をしてきたとしても、共通テストの出題形式に対応できない限り、努力の成果を発揮することは許されないのです。問題を解く以前の段階で振り落とされてしまう生徒が少なくないのが、採点方式上、部分点が付与されない「共通テスト地理」の現状と言えます。
また、「地理歴史」「公民」は、2日にわたる共通テストの一番初めの試験科目です。試験初日、朝一番の緊張している中で、複雑な問題を解くための多大な集中力と高度なパフォーマンスを求められる受験生は、本当に大変だと思います。
――示唆に富むご意見をありがとうございます。