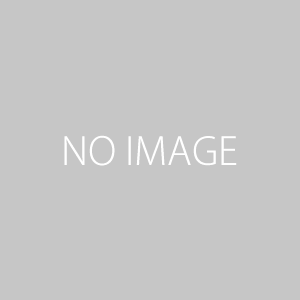河合塾講師が語る!2025年度新課程入試 ―日本史編―[後編]
■ どの分野においても、「歴史」は常に学びの対象である
――歴史科目を学んできた生徒たちに、その学びを引き継いで、大学でどのように学んでほしいと望まれますか。
歴史系学科に進む人たちと、そうではない人たちとで回答が全く違ってきます。
歴史系学科に進む人たちに対して、私が口をはさむ必要はありません。大学の先生方のご指導の下、積極的に学びを深めてほしいと思います。
他方、歴史系学科に進まない人たちには、歴史「を」学ぶのではなく、歴史「に」学んで、それを自身の専門分野の勉強に生かしてほしいです。
歴史の中でどのような選択が行われ、その選択がどのような結果をもたらしたのか。この知見は、社会生活の中で応用できる場面がきっとあるはずです。いわゆる「歴史的思考力」と言うのでしょうか。この力が身についているか否かで、あらゆる物事に対する思考の幅が変わってきます。せっかく学んだ「歴史」を、単なる教養として終わらせてしまうのはもったいないです。必要な場面で、歴史を想起できるような思考回路を鍛えておくことが望まれます。
――「高校で歴史の話は終わり!これからは自分の専門分野の勉強をするんだ!」と完全に分断してしまうのではなく、歴史に立ち返って考えるような思考を養ってほしいということですね。学生がそのような思考を育むために、大学にはどのような教育を期待しますか。
例えば経済の勉強をする場合、「経済史」は当然学ばなければなりません。法学分野にも「法制史」というジャンルがあります。つまり、現在に至るまでの歴史は、常に学びの対象であるわけです。
しかしながら、そういった「各分野における歴史」は、昨今軽視される傾向にあります。「経済史」や「法制史」を専門とする先生がいらっしゃらない大学も少なくありません。そのため、どうにも「見捨てられたジャンル」感が否めないのですが、果たして、これらは本当に蔑ろにされてよいものなのでしょうか。
どの学問分野であっても、そこに必ず「歴史」は存在します。そして、「今」はその積み重ねられた「歴史」の上に成り立つものです。だからこそ、各分野における歴史の教育、あるいはその観点での授業はきちんとなされるべきだと思います。単なる用語の蓄積だけではあまりにもったいないです。私が「歴史屋」だからそう思うのかもしれませんが、大学に求めるとすればこのようなことでしょうか。学生にしてみると、学ぶことが多くて大変かもしれませんが、「各分野における歴史」という観点からの学びも大切にしてほしいです。
――生徒たちは高校での学びや受験を通して、「日本史の力」を身につけてきたと思います。その「日本史の力」を、大学生活あるいはその後の人生において、どのように生かしてほしいですか。
先ほどの話とも重なりますが、仮に受験のために詰め込んだ知識であったとしても、身につけた知識であることに変わりはありません。自らの人生において何らかの選択を迫られた際に、学んだ歴史を、先人たちの選択を想起し、自身の判断に役立ててもらいたいです。
ありがたいことに、教え子たちからは「先生の授業、面白かったです!」「いろいろ役に立っています!」といった声をよくいただきます。しかし、一歩踏み込んで「何が面白かったのか」を聞いてみると、私がどこに行ったであるとか、そこで何を見聞きしたであるとか、そういったエピソードが強く印象に残っているようです。そのため、「自分も行ってみました!」などの話はよく聞きますが、自身が何らかの選択をする際に、歴史での学びが役に立った、というような話はなかなかありません。私としてはその点を意識して授業をしているつもりですが、現実的には、そういった場面に遭遇する機会はそうそう無いようです。けれども、いざその瞬間が来た時に、歴史で学んだことが少しでも役に立ってくれるなら、とても嬉しく思います。
■ コラム③ 日本史科へ進むきっかけは大学進学後のゼミ
――そもそも、中垣先生はどうして日本史を勉強したいと思われたのでしょうか。きっかけとなるエピソード等がございましたら、ぜひ教えてください。
もう随分と昔の話になりますが、実は、私は初めから歴史科の教員を目指していたわけではありません。高校の時に出会った国語の先生が非常に優れた方で、その方に憧れて、国語科の教員を目指していました。
そんな私が本格的に日本史に興味を抱くようになるのは、大学進学後のことです。私の進学先は1年生からゼミのある学部で、その時に私たちを指導してくださったのが、日本史を専門とする先生でした。ゼミの仲間にも恵まれ、ディスカッションやレポートなどがとても面白かったのをよく覚えています。もともと歴史が好きだったことももちろんありますが、このゼミをきっかけに、関心が国語から日本史へと徐々に移っていきました。最終的には、教員採用試験も社会科で受験しています。
――ちなみに中垣先生のご専門はどのような分野だったのでしょうか。
専門と言えるほどではありませんが、強いて言うならば日本の近現代史、特に教育史です。現在はあまり表に出てくるジャンルではありませんが、一時期「歴史教育学」という分野が話題になったことがあります。静岡大学で教鞭をとられていた故黒羽清隆教授の著書に影響を受け、この分野を勉強したいと思いました。
要するに教育の方法論です。「どのように伝えれば生徒の身につくのか」や「学んだことがどのように役に立つのか」といったことを勉強していました。しかしながら、現実に実践するのはなかなか難しいものですね(笑)。