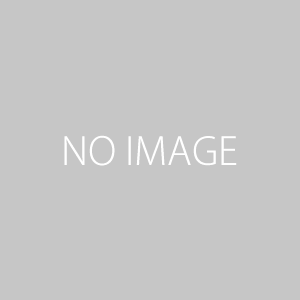QSアジア大学ランキング2026発表 香港大学が初の首位、日本から147大学がランクイン
■ アジアの大学間競争が一層激化、日本勢は「質の高さ」と「国際化」の両立が課題に
英国の高等教育評価機関 QS Quacquarelli Symonds(以下、QS)は、2025年11月4日付でアジア地域を対象とした「QS World University Rankings: Asia 2026(QSアジア大学ランキング2026)」を発表した。今回のランキングでは、アジア25の高等教育システムから1,500以上の大学が評価対象となり、そのうち550校超が新規参入と、過去最大規模の調査となっている。
総合1位は The University of Hong Kong(香港大学)。前年首位であった Peking University(北京大学) を抑え、ランキングトップの座を獲得した。3位には Nanyang Technological University,Singapore(南洋理工大学) と National University of Singapore(シンガポール国立大学) が同率で並び、香港・中国・シンガポールの研究大学が上位を占める結果となった。
一方、国別のランクイン大学数では、中国本土が394校で最多となり、これまで最多であったインド(294校)を上回った。続いて日本が147校、韓国が103校と、東アジア各国が依然として大きな存在感を示している。
■ QSアジア大学ランキングとは
QSアジア大学ランキングは、世界版ランキングとは別に、アジア地域の実情をより反映させることを目的とした地域別ランキングである。
指標は大きく「研究と発見(Research & Discovery)」「学習体験(Learning Experience)」「グローバル・エンゲージメント(Global Engagement)」「就業力(Employability)」などに分類され、
・Academic Reputation(学術的評価)
・Employer Reputation(雇用主からの評価)
・Citations per Paper(論文1本あたり被引用数)
・Staff with a PhD(博士号取得教員比率)
・Exchange Students(交換留学生:受入・派出)
といった指標が組み合わされている。世界版にはない指標(博士号取得教員比率、交換留学生など)を加えることで、アジアの大学の特徴や各国の政策的関心を反映した評価が行われている。
■ 今回の主な結果
香港:少数精鋭がトップ10の半数を占める
香港特別行政区からは11大学がランクインし、そのうち5大学がトップ10、6大学がトップ100に入った。中でも香港大学は、ほぼ全ての指標でバランスよく高スコアを獲得し、アジアのトップ研究大学としての地位を確立した。
香港科技大学、香港城市大学、香港中文大学、香港理工大学も順位を伸ばしており、限られた規模でありながら、国際共同研究や英語による教育提供を通じて、域内外から優秀な学生・研究者を集めている。
中国・インド:量と質を兼ね備えた巨大システムへ
中国本土は、394大学がランクインし、アジア最大の高等教育システムとして位置づけられた。北京大学、清華大学、復旦大学などのトップ大学は、研究力と国際的な学術ネットワークの両面で存在感を高めている。
インドは、ランクイン大学数で中国に次ぐ294大学を擁し、「研究生産性」と「博士号取得教員比率」で高い評価を受けている。IITデリーなどの工科大学を中心に、研究の量と質を拡大する取り組みが進んでいる。
韓国・台湾、東南アジアの動き
韓国では、トップ20に複数の大学が入り、トップ100にランクインした15大学のうち12大学が前年より順位を上げるなど、システム全体としての底上げが進んでいる。ソウルを中心に、学生にとって魅力的な都市環境と高いSTEM分野の研究力が相まって、国内外からの学生・研究者を惹きつけている。
台湾は、National Taiwan University(23位)を筆頭に、上位校の多くが順位を上げた。研究力に加え、国際共同研究や英語による授業提供の拡大が、指標の改善に結びついている。
東南アジアでは、マレーシアやインドネシア、ベトナム、タイ、フィリピンなどで、新規ランクイン校の増加や急速な順位の上昇が目立つ。高等教育への投資拡大や、海外大学との共同キャンパス設置などを通じて、アジアの中堅システムとして存在感を増しつつある。
■ 日本のポジション:東京大学はアジア26位、日本から147大学がランクイン
日本からは147大学がランクイン。中国・インドに続く、アジア3番目の規模を維持している。日本勢のトップは**東京大学(26位)**で、依然としてアジア全体のベンチマークとして位置づけられている。
QSの発表では、日本の大学は教育の質と研究の影響力において高い評価を受ける一方で、
・国際教員比率・留学生比率
・国際共同研究ネットワーク
・研究成果の国際発信力(論文被引用数など)
といった指標で、香港・シンガポール・韓国などのトップ大学とのギャップが課題として示唆されている。
政府は「留学生の受入40万人・派出50万人」など、双方向の学生モビリティ拡大を掲げる政策を継続しており、英語開講プログラムや共同学位プログラムの拡充を通じて、日本の大学へのアクセスのしやすさを高めていくことが期待される。
詳細は下記リンク先にて確認できる。
・QS公式サイト「QS World University Rankings: Asia 2026 results」
・Top Universities Asia University Rankings 2026