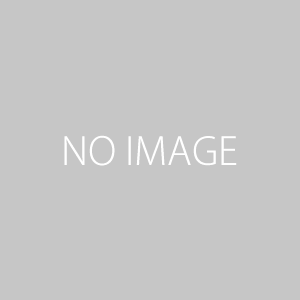文部科学省 「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」第4回を開催
2025年7月28日、「2040 年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」の第4回が開催された。今回の会議では、第1回の検討会議以来議論されてきた内容を、事務局が「中間まとめ」として整理したものが提示され、それに関する検討が行われた。

「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」(第4回)配布資料
「社会とともに歩む私立大学の変革への支援強化パッケージ(案)」と題された本中間まとめでは、私立大学を取り巻く現状と役割の変遷を踏まえ、我が国における「知の総和」の向上や地域活性化のためには、私立大学に対する公的支援の拡充、特に、基盤的経費をはじめとする私学助成の拡充が必要不可欠であると述べられている。一方で、国民の税負担を原資とする私学助成は、経営危機に瀕した私立大学等の延命のためだけに用いられることはあってはならず、教育研究の成果を持続的に社会に還元できる大学等に適切に配分されるようにすることが不可欠であるとも記述されていた。
こうしたことも踏まえた上で、今後の私学助成の基本的な考え方としては、従来の一律の配分から、以下のような観点に応じるかたちで、メリハリを付け、条件を満たす大学へ重点的に配分するよう転換を図っていくという。
・地方において、地域ニーズに応え、地域経済の担い手となる人材の輩出
・教師、保育士、看護師等のエッセンシャルワーカーの養成
・国際競争力の強化に資する研究環境の充実
・日本の産業を支える理工農系分野における人材の育成
・大学の教育研究の質の向上に向けた取組
また、中長期的には、従来の設置者に応じた支援から転換し、教育研究の機能や成果に着目した支援の仕組みの創設を検討すべきともされている。

「2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議」(第4回)配布資料
さらに、上述の国の財政支援に係る基本的な考え方や、高等教育の規模の適正化の観点を踏まえつつ、時間軸をもちながら、私立大学振興のための3つの施策の方向性の転換を図っていくという。
第一に、「地域から必要とされる人材育成を担う地方大学の重点支援への転換」では、地域経済の担い手や、エッセンシャルワーカー育成支援等における「自治体・産業界等との連携の推進」、および教育の質の向上や効率的な大学経営を目的とした、地域の「大学間の連携の推進」が挙げられている。特に前者においては、地域の高等教育機関、地方公共団体、産業界等による連携の強化策として、プラットフォームの構築や、それぞれの協力による人材育成に係る取組への支援を図っていく。さらに、地域の人材需要や産業ニーズ等に応じた教育研究を行う私立大学については、定員充足率に応じた私学助成の在り方の見直し等も通じた、教育研究環境の充実を図るとされている。
第二に、「日本の競争力を高める教育研究を担う大学の重点支援への転換」では、大きく2つの方針が打ち出された。「国際競争力の向上に向けた私立大学の研究力強化」においては、研究力の高い私立大学が、国際的にも研究力で競い合える拠点となるための学術的基盤の確立に向けて、基盤的経費を一体的かつ集中的に支援する枠組みの構築が掲げられている。このほか、設置者の別なく、研究基盤が大学の枠を超えて共同利用されるための支援や、優秀な研究者を確保するための高額給与支給に係る私学助成の減額の仕組みの見直し、大学院の定員増等の機能強化に向けた支援の充実等も示された。
また、「日本の産業を支える理工農系人材の育成」においては、我が国では大学の専攻分野別の入学者数の割合が文系に偏っており、理工農系の産業人材を希求する地域で人材ニーズと学部分野とのミスマッチが指摘されていること等も踏まえ、理工農系分野で学ぶ学生の拡大を目指すべく、各種方向性が示された。理工農系分野の学部の教育研究費支出が多い傾向にあることを考慮した、教育研究環境の充実に向けた産官による重点的な支援や、ST比等の改善を通じた私学助成の効果的な配分強化のほか、定員超過の大学への減額措置の厳格化、産学融合による教育の充実に向けた、企業等の大学教育への参画・支援に対する税制上の優遇措置の活用促進およびマッチングファンド等の支援を検討するという。
そして第三に示される、「再編・統合等による規模の適正化に向けた私立大学の経営改革強化への転換」においては、従来も挙げられていた、経営が困難な状況にある、またはそのリスクのある大学への経営指導の強化や、学部等新設の厳格化に加えて、学校法人間の連携・合併や円滑な撤退に向けた支援のほか、学生または卒業生の不利益を最小限にする取組が示された。大学の規模の適正化に向けた支援、とりわけ撤退する大学に対する支援の具体的な方向性が示されたことが注目される。
出席した委員からは、「プラットフォームの構築については、国公立大学や産業界にもメリットがあるよう工夫して進めていくべきである」、「私立大学の役割は国立大学の補完が全てではない。地方私立大学がこれまで担ってきた役割に、もっと踏み込んでほしい」、「理系重点分野への転換を図るという点について、人文社会学系の教員は戦々恐々としている。ソフトランディングになるよう配慮してほしい」といった、内容・表現に関するコメントが出された。
また、地域との関係においては、「地域連携プラットフォームを作ると言っても、具体的に何をするかを明確に打ち出していかねばならない段階に来ている」、「地域への人材輩出に係る地方自治体との連携に関して、都道府県よりも大学が所在する市町村に、将来に対する危機感が足りない。もっと自分事ととらえていく必要があり、国からの働きかけも強化すべき」等、実感のこもった意見も聞かれた。
さらに、「経営力強化の方策として資産運用が挙げられているが、以前、資産運用に失敗して巨額の負債を抱えた法人もあるため、強調し過ぎるのは危険だ」といった注意喚起もなされていれた。
今回の中間まとめは、来年度予算の編成に向けた検討材料として出されたものであり、今後も引き続き検討が重ねられる。次回8月26日の会議では、私立大学の教育研究の質の向上⽅策等について議論される予定だ。
配布資料等は、下記リンク先にて確認することができる。
2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会議(第4回)配布資料
配布資料等は、下記リンク先にて確認することができる。
・
Author:小松原潤子(KEIHER Online 編集委員)・山口夏奈(KEI大学経営総研 研究員)