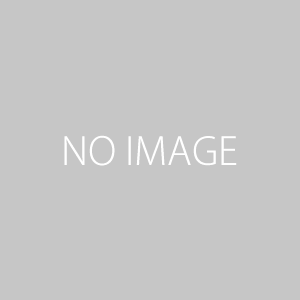豊島岡女子学園 中学校・高等学校 インタビュー[前編]
■高難易度の課題への挑戦を支える連携体制
--『AcademicDay Final』に参加して気になったのが、実験の中で生成AIを使っている学生がいました。最近は生成AIを教育にどう使っていくかということが注目されていますが、何か指導はされていますか?
十九浦:今のところはしていません。どちらかというと高校生より中学生のほうが活用している生徒が多いと思います。自分たちでこれ以上手が出なくなってしまったところ、特に最近見たのはコーディングで、細かいテクニカルなところの処理が間に合わかったところを、Chat-GPTに投げて、返ってきたもので実際にやってみたら上手く動いたということがありました。
--生成AIも学生が自律的、自主的に活用しているということですね。
十九浦:そうですね。ですが、やはり生成AIだけでは思い通りにいきません。先ほど話にあがった『T-STEAM:Pro』はかなり課題の難易度が高いので、どうやってこれを突破しようかということでChat-GPTにコーディングを投げてみる生徒がいます。返ってきたものを動かしてみると、想定とは違う動きになってしまったり、実際にプログラムはちゃんと動いているけれど、駆動系に伝えて動かした側のほうでちゃんとタイヤがまわっていなかったり、想定通りにまっすぐ動かず斜めに進んでしまったり。
もの作りと生成AIを組み合わせていくと、想定通りそのままでないことも起こる。そういう試行錯誤があるからこそ、『T-STEAM:Pro』や『T-STEAM:Jr』はやっている価値があるのだろうと思っています。
--『T-STEAM:Pro』はかなり難易度が高いとのことですが、学生はテーマに対して取り組む前に何か講義を受けるのでしょうか。
増田:最初にキックオフということで、毎年東京電機大学さんにご協力をいただいています。その年のテーマの専門の先生に来ていただいて、仕組みの一番の初歩、この先の取り組みの助けになるところに関して講演をしていただきます。その講演をもとに、それぞれが動きだすという形をとっています。
コンテストの時にもその先生には来ていただいて、生徒たちがキックオフの後で取り組んできた成果を見ていただき、フィードバックをいただいています。
--東京電機大学さんとは、2019年に中高大連携に関する協定を締結されています。つながりが強く、いろいろと連携されているのですね。
増田:毎年『T-STEAM:Pro』が終わっても、思うような結果が得られず悔しい思いをして、探究活動でこのテーマをもっと研究していきたいと思う生徒たちがいます。去年のテーマで取り組みを続けている生徒もいれば、今年のテーマを探究活動として継続していく生徒もいて、そういった生徒たちはそれぞれお世話になった先生に「また聞きたいことがあるので行っていいですか?」と引き続き指導していただいたりもしています。
--学外との連携について、JAMSTECさんや東京電機大学さん以外に連携されているところはありますか?
十九浦:京都大学さんとも連携していて、毎年3月に開催されているポスターセッションに参加させていただいています。
また、今度新しく始まるのが、旭硝子財団の『ブループラネット賞』です。『若い世代のための地球環境問題ワークショップ等』で採択され、いろいろ支援をお願いすることになっています。(2024年 「若い世代のための地球環境問題ワークショップ等」選考結果のお知らせ | ブループラネット賞 | 公益財団法人 旭硝子財団)
豊田: 工学院大学さんとも2019年に教育連携に関する協定を締結し、探究活動などでご協力いただきました。