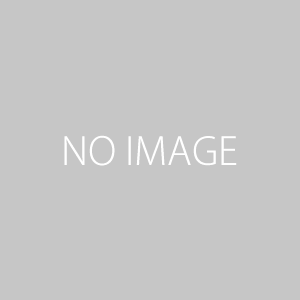文部科学省 認証評価制度や高等教育機関の規模見直しを検討
1月28日、「中央教育審議会大学分科会(第181回)・高等教育の在り方に関する特別部会(第15回)合同会議」が開催された。新たな質保証・向上システムの構築が必要だとして、認証評価制度を見直す方針であることがわかった。また、今後の少子化等による高等教育機関の超過供給状態を受け、撤退も含めた議論が必要であるとし、その支援を強化することとした。
「我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申【案】)」の中で、人の数と人の能力の掛け合わせである「知の総和」を向上させるため、高等教育機関の教育研究の質を上げ、社会的に適切な規模の高等教育機会を確保し、また地理的・社会経済的な観点からのアクセス確保によって高等教育の機会均等の実現を図ることが必要であるとした。
「評価のための評価」から脱却、認証評価を抜本的見直し
「知の総和」の向上にあたっては、学生一人一人が能力を最大限高めていけるようにすることが必要であるとして、学習者本位の教育を更に発展させることを目指す。そのためには、新たな高等教育の質保証・向上システムを構築する必要がある。
関連して、現行の認証評価制度については評価疲れの声があり、「評価のための評価」から脱却する必要があるとして、評価の在り方や内容、活用方法等を含め、質確保と負担軽減のバランスを踏まえた制度の抜本的な見直しの必要性が議論された。
現行の認証評価は、大学の教育研究等の総合的な状況を対象とし、大学評価基準への適合状況を適合あるいは不適合で評価しているが、新たな評価制度では、学部・研究科等を対象とし、定性的評価・教育情報データベースを活用した定量的評価に基づき、在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか等の教育の質を数段階で示す。それに伴い、情報公表を推進するため、新たな評価におけるデータベースと連携した新たなデータプラットフォームを構築し、学修者や進学希望者が各大学の教育力を把握できるような情報を公表することを検討している。
撤退を含め議論、高等教育全体の適正な規模見直し
また、大学入学定員が増加していることを受け、今後は急速な少子化の進行等の中で定員充足率のより一層の悪化が見込まれており、各高等教育機関の経営状況の悪化により、教育研究の「質」が維持できなくなるおそれがある。そのため、これまでの前提である18歳、国内、対面の学生にこだわらず、留学生や社会人学生等の多様な学生が入学できるようにすることが必要であるとした。一方、今後の超過供給状態において、設置基準や審査の在り方の抜本的な見直しによって安易な設置を抑制し、また設置者の枠を超えた、高等教育機関間の連携、再編・統合、縮小、果ては撤退の議論を避けることはできず、高等教育全体の適正な規模の見直しが必要であるとした。
高等教育機関全体の規模の適正化に関する具体的方策としては、以下のような対応が示された。
・教員の配置基準等についての制度改善、財産保有要件や経営状況等に関する要件の見直し、経営状況が悪化した場合等のリスクシナリオや学生確保の見通し等に関する審査プロセス等の見直しによる、厳格な設置認可審査への転換
・学部等の設置後に完成年度を迎えても定員充足率が一定の割合に満たない場合等、設置計画の履行が十分になされていない場合における、私学助成の減額・不交付措置等
・大学院シフトや留学生、社会人増加大学等への支援や、複数大学等の連携による経営改革の支援等、意欲的な教育・経営改革への支援強化
・一時的な定員減の仕組みの構築や、規模縮小、撤退に係る指導の強化、経営改善計画の策定義務付け、学生募集停止を行った学部等に対する継続的な教育研究活動支援等による縮小・撤退支援
詳細は下記リンクより。